尺八奏者のための五線譜読解1-音符の種類と長さ
今回から、要望の高い「五線譜での演奏」にチャレンジしていきます。
まずはじめにお断りしておきましょう。
筆者は、五線譜および洋楽の専門教育を受けたことがありません。
筆者が演奏できる楽器は、尺八のみです。
そんな輩が偉そうに綴るこれからの文章は、洋楽的先入観なしの、ゼロからはじめる「尺八のためだけの」五線譜読解法です。
尺八に不要な部分は、頼もしい勇気をもってざっくり無視して記述します。
ところで、五線譜に関しては、上達塾009「五線譜が読めない」 で既に取り上げてあります。先の記事では、「五線譜は訓練によってスラスラと読めるようになるので、頑張って苦労してください」とまとめましたが、あまりにナゲヤリだったので、その「努力すべくスタートラインに立つにはどうすればよいか」を今回は具体的に取り上げていきます。
0.楽譜が読めるということ
楽譜として成立する最低限の要素は、「音の高さ」と「音の長さ」の2つです。
演奏者はせめて最低限、この2つの要素を楽譜から読み取ることができなければ、楽器を演奏することができません。
即ち、五線譜が読めるイコール、音の高さと長さを正確に読み取ることができるということです。
さしあたっての目標は、この2つの要素を五線譜から正確に読み取れるようになることです。
1.音符の種類と長さ
1拍(4分音符・しぶおんぷ)
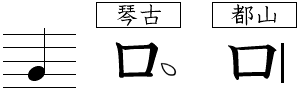 4分音符と尺八譜との対応
4分音符と尺八譜との対応
拍とは、「脈拍」「拍手」というように、「繰り返し」のことです。その繰り返しの最小単位を「1拍(いっぱく)」または「1拍子
(いちひょうし)」と規定します。音楽的には、1拍を、メトロノームの一往復と定義し、琴古流の楽譜表記はこの考え方に倣っています。
2分の1拍(8分音符・はちぶおんぷ)
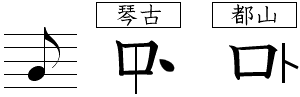 8分音符と尺八譜との対応
8分音符と尺八譜との対応
1拍の半分が、半拍、2分の1拍子です。
4分の1拍(16分音符・じゅうろくぶおんぷ)
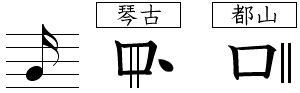 16分音符と尺八譜との対応
16分音符と尺八譜との対応
2分の1拍のさらに半分が、4分の1拍、4半拍子です。
尺八演奏上、最も細かい音符と考えてよいでしょう。慣例的に、この音符が使われている部位を「じゅうろくぶ」と呼ぶことがあります。
2拍(2分音符・にぶおんぷ)
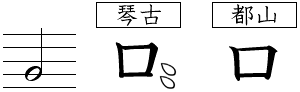 2分音符と尺八譜との対応
2分音符と尺八譜との対応
1拍の2倍です。
4拍(全音符・ぜんおんぷ)
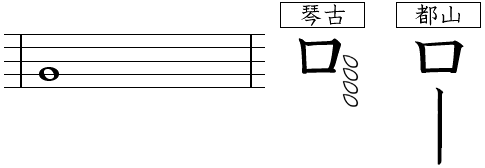 全音符と尺八譜との対応
全音符と尺八譜との対応
2拍の2倍です。
付点音符(ふてんおんぷ)
おたまじゃくしの右横に小さな丸点を打つと、長さを1.5倍(=2分の3倍)にします。
付点4分音符(ふてんしぶおんぷ)
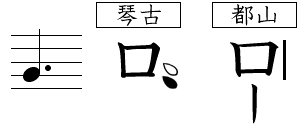 付点4分音符と尺八譜との対応
付点4分音符と尺八譜との対応
1拍×1.5で、1.5拍です。
付点8分音符(ふてんはちぶおんぷ)
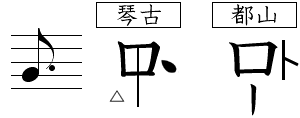 付点8分音符と尺八譜との対応
付点8分音符と尺八譜との対応
0.5×1.5で、0.75(4分の3)拍です。
付点2分音符(ふてんにぶおんぷ)
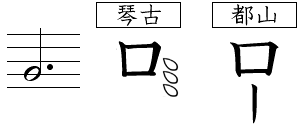 付点2分音符と尺八譜との対応
付点2分音符と尺八譜との対応
2拍×1.5で、3拍です。
休符
考え方は、全て今までの音符と同じです。
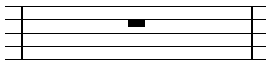 全休符(4拍)
全休符(4拍)
 2分休符(2拍)
2分休符(2拍)  4分休符(1拍)
4分休符(1拍)
 8分休符(2分の1拍)
8分休符(2分の1拍)  16分休符(4分の1拍)
16分休符(4分の1拍)
 付点2分休符(3拍)
付点2分休符(3拍)  付点4分休符(1.5拍)
付点4分休符(1.5拍)
 付点8分休符(4分の3拍)
付点8分休符(4分の3拍)
※休符とは、休みのことではなく、「音を出さないこと」であって、休符が記譜されてある限り、演奏中であることを忘れないでおいてください。
以上の音符・休符を組み合わせて、五線譜は構成されます。
次回は、特殊な音符、尺八吹きが、はて、と一瞬戸惑ってしまいがちな音符の例をご紹介します。
Copyright(c) 2005 OFFICE RINDO. All Rights Reserved.