尺八奏者のための五線譜読解2-特殊な音符とその長さ
前回 上達塾041:
尺八奏者のための五線譜読解1-音符を知る では、音符の種類をご紹介しました。今回は、
その音符が実際に使用される上で、知っておくべき内容をご説明します。
音符の「棒」の向き
全音符以外の音符には、「棒」があります。棒は上向きと下向きの2種類がありますが、
これは全体の見栄えを考慮して決定されるもので、上向きか、下向きかによる意味の違いはありません。一般的に、
五線の真中で上下を切り替えます。
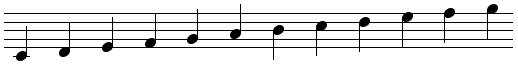 音符の棒の向き
音符の棒の向き
※参考:複数パートを一つの五線に表記しようとする場合、第一パートを上向き、
第二パートを下向きという具合に固定することがあります。
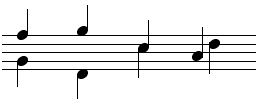 パート別に棒の向きを固定した例
パート別に棒の向きを固定した例
旗の連結
1拍未満の音符には、「旗」が立っており、隣り合う音符は、旗と旗を連結して表記する場合があります。
・同種の音符の連結例1
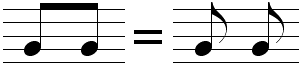
・同種の音符の連結例2
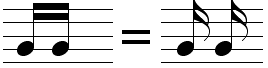
・同種の音符の連結例3
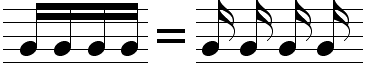
・異種の音符の連結例1
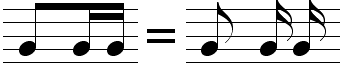
・異種の音符の連結例2
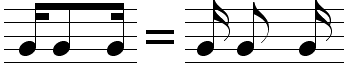
・異種の音符の連結例3
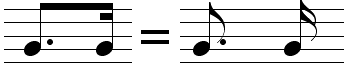
装飾音符
拍子外音符ともいいます。拍数を数えず、瞬間的に素早く演奏します。多くは、直後の音を導く役割を果たします。
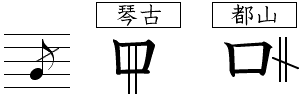 装飾音符の例1
装飾音符の例1
装飾音符は、1音の場合は、やや小さめの8分音符に斜線を入れます。2音以上の場合は、斜線を入れません。
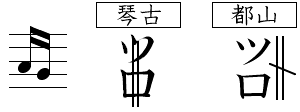 装飾音符の例2
装飾音符の例2
タイ記号
タイとは英語のtieのことで、「結ぶ」という意味です。(ネクタイneck-tieのタイです)
この記号で結ばれた二つの音符は、両方の合計分の長さをのばすことになります。
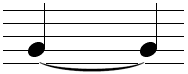 タイ記号の例1
タイ記号の例1
タイ記号の例1では、1拍と1拍がタイ記号で結ばれているので、合計で2拍です。
※参考:タイ記号に似ている記号で、「スラー記号」があります。これは「複数の音をなめらかに演奏しなさい」
という指示をあらわす記号で、タイ記号に似ていますが内容は別物です。見分け方は、タイは同じ高さの音どうし、
スラーは原則的に異なる高さの音どうしを連結しています。スラー記号は、それぞれの音の長さに影響を与えません。
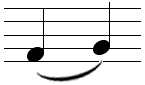 スラー記号 異なる高さの音を結ぶ
スラー記号 異なる高さの音を結ぶ
また、タイ記号は、長さの異なる音符どうしでも、小節をまたいでも有効です。
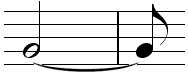 タイ記号の例2
タイ記号の例2
タイ記号の例2では、2拍と0.5拍が合計で、2.5拍です。
さてここで、小節という概念がはじめて出てきました。特に琴古流の古典の楽譜では、小節という概念がなく、
曖昧になりがちな部分です。次回は「小節」についてから始めます。
Copyright(c) 2005 OFFICE RINDO. All Rights Reserved.
Comments
“042: 尺八奏者のための五線譜読解2-特殊な音符とその長さ” への2件のフィードバック
あれ?せっかく良いサイトを見つけたと思って喜んだら,最新記事からずいぶん時間がたっていますね。
もうやめてしまったのでしょうか?
じつは今日から尺八を始めるので,これからお勉強しようと思ったのにな~。
と,暗に「続けてください」とお願いしてみる(笑)。
他の仕事がお忙しいと無理なお願いになってしまいますが。
30代で比較的若め(?)の初心者なんです。身近な友人から情報を得ることは難しそうなので,こういうサイトはとてもありがたいんですが。
ぜひぜひ。
どうも、良いプレッシャーを、ありがとうございます。
一連の原稿は、尺八を吹き始めて10年目に、考えていることを固定しておこうと
思い立ち書き始めたものです。(10年目からは既に数年経過してしまってますが。)
よって、ひととおり思うところを吐き出した感があるので、それに伴って新規の原稿も
フェードアウトしてしまいました。
尺八を始めたばかりとのこと、私からのアドバイスは、
とにかく、いい音をたくさん聴いてください。
良い音とは、すごい、と素直に思える音です。
一度聴き終わった後、もう一度聴きたい、と思える音です。
良い音かどうかを判断するのは、ご自身の耳です。
一度聴き終わって、すごい、また聴きたいと思えない音は、
特にいい音ではないので、また別の音を探してください。
良い音を聴き、それを頭の中に持っている人は、尺八と向き合う姿勢が明らかに違います。
中途半端で何となく続けていくか、心底尺八という楽器にのめりこんでいくかの分岐点は、
そのあたりにあるのではないかとも思います。
だからといって、CDを買いあさるとなるとなかなかに高価ですから、お近くの図書館等や、
ラジオ、テレビなどを丹念に探す、或いは演奏会に赴くなど、探せば結構あるものです、
是非、良い音探しを始めてみることをお薦めします。
他、具体的に、何かご質問がおありなら、このブログなり、またメールでも結構です、
お寄せいただければ回答いたします。
とりあえず、読んでいただける方がいらっしゃる以上、前回の原稿から
一年経過する前には、新しい原稿を書きたいとは、思っておりますが。なんとも。