尺八奏者のための五線譜読解3-小節の基礎知識
小節とは
五線譜は、一定の間隔で、縦棒により細かく区切られています。この縦棒で区切られた一つ一つの空間を、「小節」と呼びます。
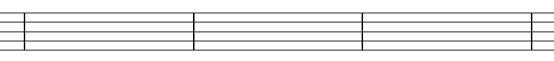
縦棒で区切られた一つ一つの空間が小節
音楽は、足し算だ
一つの小節の中には、入れることのできる拍数が曲ごとに指定されており、それはト音記号のすぐ右に、分数(ぶんすう)
で記載されています。
この分数は、「拍子記号」(ひょうしきごう)と呼ばれます。
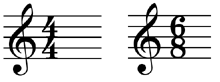
拍子記号の例:分母と分子が持つ意味合いが異なるので、約分してはいけない
意味は、分母(下の数字)の音符を分子(上の数字)の数だけ、一小節に入れなさい、という意味です。
例えば4分の4なら、4分音符(分母)を4つ(分子)ぶん、8分の6なら、8分音符(分母)を6つ(分子)ぶん、一小節に入れる、という意味です。
4分の4とか、8分の6とか、現役の小学生なら迷わず約分してしまいそうなものもありますが、分母と分子が持つ意味合いが異なり、厳密には分数ではないので(だから拍子「記号」という名前がついています)、約分してはいけません。
入れる音符の種類は、指定された音符である必要はありません。4分の4なら、必ず4分音符しか使ってはならない、という意味ではなくて、合算してそれと同じ長さになるなら、8分音符や2分音符などの、4分音符以外が混ざっていても構いません。
ここで重要なことは、「指定された長さぶんぴったりの音符が必ず全ての小節に入っていなければならない」ということです。
4分の4であれば、1拍(4分音符)×4で4拍が必ず全ての小節に入っている必要があります。
この小節だけちょっと多めで4.05拍だったり、あるいは3.9999だったりしても、それは許されません。必ず、4.00拍ぴったりである必要があります。
4分の4であれば、全音符(4拍)が1つあるだけの単純なものから、2+0.75+0.25+0.25+0.5+0.25で合計4拍、という複雑なものまで、ようするに全て足し算です。
3連符、5連符などが混じることもあります。休符があれば、それもきっちりと加算してください。この足し算を無意識の中で繰り返すことで、曲は進行していくのです。
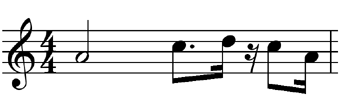
4分の4拍子、複雑な足し算の例:
2+0.75+0.25+0.25+0.5+0.25で合計4拍
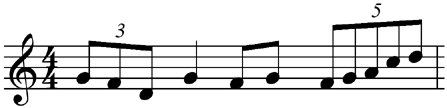
3連符、5連符が混在する例:
※n連符とは:ある長さをn個に均等分割(n=3以上の奇数)するとき、分割する全体の長さの音符より一段階短い音符を連結し、nにあたる数字をその外側に表記して表現する。一拍を3等分する3連符は、4分音符より一段階短い音符である、8分音符を3つ連結し、音の長さとしては1拍となる。
演奏する上で、常に小節の中に格納されている拍数を足し算で計算し続ける、この意識は、できる人は最初から当たり前にできているので全く意に介することなく済んでしまうことなのですが、楽譜が読めないという人の中には、この足し算の意識が希薄な人がいるようです。
特に琴古流の尺八記譜法に慣れてしまっている人は、この傾向にある可能性があります。
楽譜を読む最初の基本は、算数です。曲が始まって一度足し算を始めたら、それをやめるときは、曲が終わる時です。
足し算の例外
上記「4分の4なら、必ず4拍を一小節に入れる」の例外があります。曲の開始、第一小節目だけは、これにこだわらずに柔軟に解釈することになっており、第一小節は規定の拍数よりも少ない場合があります。これを弱起、或いはアウフタクト(最後の拍子は指揮棒を上aufに振ることから)と呼びます。
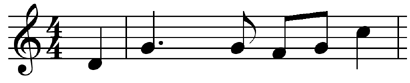
アウフタクトの例:第一小節は、規定の4拍に満たない
特殊な拍子記号
4分の4は非常によく使われるので、アルファベットの「c」(commonの頭文字)で代用されることがあります。さらには、それすらも省略されて、何も書かれない場合があります。
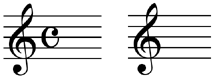 4分の4の省略
4分の4の省略
拍子の変更
拍子は、曲の途中で変更されることがあります。この場合、変更される小節の冒頭に新しい拍子の拍子記号を記載します。
拍子記号は、その後また別の拍子記号が出現しない限り、最後まで有効です。途中で勝手に元の拍子に戻るようなことはありません。
元の拍子に戻すときは、改めてその拍子記号を記載する必要があります。
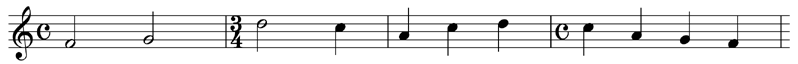
拍子の変更:4分の4拍子で開始された曲は、第二小節で4分の3拍子となり、第三小節は指示が特にないのでそのまま4分の3拍子で進行、第四小節で4分の4拍子が新たに指示された。
メトロノーム記号
曲の演奏速度を指定するのが、メトロノーム記号です。原則的に拍子記号の分母に指定される音符を用いて、それを一分間にいくつ入れるかを数字で示します。
4分音符=60なら、メトロノームがカッチン、カッチンと1分間に60回鳴るスピードで、そのカッチンと鳴る1回を1拍として演奏しなさい、という意味です。
8分音符=90なら、メトロノームがカッチン、カッチンと1分間に90回鳴るスピードで、そのカッチンと鳴る1回を半拍として演奏しなさい、という意味です。
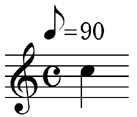
メトロノーム記号
休小節
複数小節連続した休みが続く場合、太線の上に休止の小節数を数字で記載します。
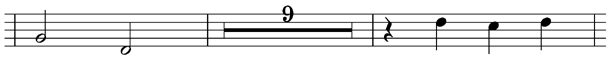
休小節の例:9小節分の休みが1小節分の長さで表現されている
総休止 G.P.
読み方は、英語ならジーピー、ドイツ語ならゲーペー、あるいはドイツ語で略さずにゲネラルパウゼ(GeneralPause)と読みます。
その小節は全ての楽器が休拍であることを意味します。演奏上は、普通にその小節は全休とします。
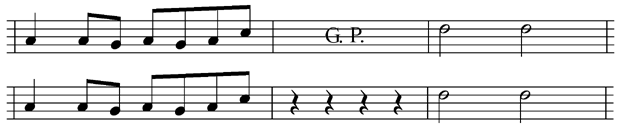
総休止の例:上の楽譜の演奏内容は下の楽譜のものと同じ
さて、小節についての基本概念は以上のとおりです。細かい知識はきりがないので全て省略してありますが、尺八演奏の上では、必要な知識はこれで全て満たしていると思ってよいでしょう。
次回は、「繰り返し記号」についてまとめます。
Copyright(c) 2006 OFFICE RINDO. All Rights Reserved.